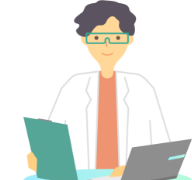体脂肪のヒト試験とは?分かりやすく徹底解説
自社で開発した有望な素材が、体脂肪を減らす効果を持つ可能性がある。しかし、その効果を科学的に証明し、消費者に響く製品として市場に投入するには、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか。特に日本では、機能性表示食品制度という独自のルールが存在し、その基準を満たすためのハードルは決して低くありません。
この記事は、まさにそのような課題に直面している製品開発担当者様、研究開発者様、そしてマーケティング担当者様のために、専門家の視点から執筆された包括的な解説です。
本稿を最後までお読みいただくことで、以下の点が明確になります。
- なぜ体脂肪に関するヒト試験が必要なのか(機能性表示食品制度との関連性)
- どのような方法で体脂肪を科学的に測定するのか(最新の測定技術の比較)
- ヒト試験にはどれくらいの費用がかかるのか(目的別の詳細な費用相案)
- 成功の鍵を握る研究パートナー(CRO)をどう選ぶべきか
漠然とした計画を、実行可能で具体的なロードマップへと変えるための一助となれば幸いです。
20年以上の実績と経験があるアポプラスステーション株式会社
→基礎代謝のヒト試験について無料でお問い合わせする
ヒト試験の価格や種類については下記記事で詳しく解説しています。
ヒト試験とは?種類や価格・臨床試験との違いについて解説
ヒト試験で体脂肪を評価するとは?目的と科学的根拠の重要性
ヒト試験を通じて体脂肪を評価する行為は、単なるデータ収集に留まりません。それは、製品の価値を法規制、ガイドライン、指針などの枠組みの中で科学的に証明し、最終的に消費者の信頼を獲得するための戦略的な投資活動です。特に、健康食品市場で競争優位性を確立するためには、その目的と科学的根拠の重要性を深く理解する必要があります。
機能性表示食品における「体脂肪」ヘルスクレームの鍵
製品パッケージに「体脂肪を減らすのを助ける」、「脂肪の消費をサポートする」といった魅力的な表示(ヘルスクレーム)を記載することは、消費者の購買意欲を大きく左右します。このヘルスクレームを実現するための重要な制度が、「機能性表示食品制度」です 。
この制度は、国の審査を経て許可される特定保健用食品(トクホ)とは異なり、事業者の責任において科学的根拠を消費者庁に届け出ることで、機能性を表示できる仕組みです 。つまり、表示の正当性を担保する責任は、すべて事業者側にあります 。
その科学的根拠として認められるのは、主に以下の2つです 。
①最終製品を用いた臨床試験(ヒト試験)
②最終製品または機能性関与成分に関する研究レビュー(システマティック・レビュー)
本記事では、特に①の「最終製品を用いた臨床試験」に焦点を当てて解説します。適切なヒト試験を実施し、質の高いエビデンスを構築することができれば、「腹部内臓脂肪と腹部総脂肪を低減する機能があります」や、「肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪(内臓脂肪、腹部総脂肪)、ウエスト周囲径の減少をサポートする」といった、具体的で説得力のあるヘルスクレームの表示が可能になります。
この制度の根幹にあるのは、事業者が自ら科学的根拠の質を保証するという考え方です。そのため、実施されるヒト試験は、科学的にも規制上も妥当性の高い、厳格な設計が求められます。例えば、客観性を担保するために、効果を検証したい食品(本物)と、見た目や味は同じでも有効成分を含まない食品(プラセボ)を比較する「プラセボ対照」、試験参加者も試験実施者もどちらが本物か分からないようにする「二重盲検法」、試験参加者をランダムに割り付ける「ランダム化比較試験(RCT)」といった手法が、科学的根拠の信頼性を高める上で標準的な方法とされています。事業の成功は、この科学的厳密性への投資にかかっていると言っても過言ではありません。
試験の基本的な流れと試験参加者条件
体脂肪を評価するヒト試験は、一般的に以下の流れで進行します。
- 試験計画の策定:どのような対象者に、何を、どれくらいの期間摂取してもらい、何を測定するのかを定めた「プロトコル(実施計画書)」を作成します。
- 試験参加者の募集・選定:計画に基づき、試験の目的に合致した試験参加者を募集し、基準を満たすかを確認(スクリーニング)します。
- 試験期間:試験参加者に試験食品またはプラセボ食品を一定期間(例:4週間、8週間、12週間)摂取してもらいます。
- 測定・検査:摂取前、摂取期間中、摂取後に来院してもらい、体脂肪やその他の関連項目を測定します。
- データ解析・報告:収集したデータを統計的に解析し、有効性や安全性を評価して報告書にまとめます。
この中で特に重要なのが、試験参加者の条件設定です。体脂肪関連の試験では、効果が期待される集団を対象にするため、特定の条件が設けられます。例えば、「BMIが23以上30未満」や、「内臓脂肪面積が100㎠以上」といった基準が用いられます。これは、対象者を絞り込むことで、製品の効果が統計的に有意な差として現れやすくするためです。
また、試験期間の設定も科学的妥当性と密接に関連します。体脂肪のような代謝に関わる指標は、短期間では変化が現れにくいため、特に体脂肪関連の有効性試験では12週間以上の摂取期間が求められることが一般的です。
これらの科学的妥当性を追求するための条件(厳格な試験参加者選定、十分な試験期間)は、プロジェクトのコストや期間に直接的な影響を及ぼします。例えば、試験参加者の基準を厳しくすれば募集の難易度が上がり、期間を長くすれば試験参加者の途中脱落リスクが高まるため、より多くの費用と時間が必要になります。したがって、ヒト試験の計画段階では、科学的な厳密性とビジネス上のリソース(コスト、時間)との間で、最適なバランスを見出すことが極めて重要になるのです。
20年以上の実績と経験があるアポプラスステーション株式会社
→ヒト試験について無料でお問い合わせする
【徹底比較】ヒト試験で使われる体脂肪の主要な測定方法
ヒト試験で「体脂肪への効果」を主張するためには、その変化を客観的かつ正確に捉える測定方法の選択が不可欠です。測定方法にはそれぞれ特徴があり、試験の目的や求めるエビデンスレベル、予算に応じて最適なものを選択する必要があります。ここでは、主要な測定方法を精度や信頼性の観点から比較・解説します。
ゴールドスタンダード:CT法とDXA法の違い
機能性表示食品の届出など、規制当局への提出を目的とした信頼性の高いエビデンスが求められる場合、「ゴールドスタンダード」と呼ばれる最も精度の高い測定方法が用いられます。体脂肪測定における二大ゴールドスタンダードが、CT法とDXA法です。
- CT法(X線CT法)
CT(Computed Tomography)スキャンは、特に「内臓脂肪面積」の測定において、現在最も信頼性の高いゴールドスタンダードとされています。X線を用いて身体の断面画像を撮影し、へそ周りの画像から内臓脂肪と皮下脂肪を明確に分離して、それぞれの面積を正確に算出できます。この精度の高さから、「お腹の脂肪(内臓脂肪)を減らす」といった特定の部位への効果を訴求するヘルスクレームの科学的根拠として、非常に強力なエビデンスとなります 。 - DXA法(二重エネルギーX線吸収法)
DXA(Dual-energy X-ray Absorptiometry)法は、もともと骨密度の測定に用いられてきた技術ですが、体組成の評価にも応用されています 。2種類の異なるエネルギーのX線を照射し、骨、脂肪組織、除脂肪組織(筋肉など)の透過率の違いから、全身および部位別(腕、脚、体幹など)の体脂肪量、筋肉量、骨量を高い精度で測定できます。古典的な基準である水中体重秤量法との相関も高く、体水分量の変動に影響されにくいという利点もあります 。全身の体脂肪率の変化や、アスリートのように部位ごとの筋肉量の変化も同時に評価したい場合に特に有用です 。
この二つの方法は、どちらも高精度ですが、得意とする領域が異なります。製品の作用機序や、最終的に表示したいヘルスクレームが「内臓脂肪」に特化している場合はCT法が最適です。一方で、「体脂肪率」の低減や全身の身体組成バランスの変化を包括的に示したい場合はDXA法が適しています。したがって、どちらを選択するかは、単なる精度の問題ではなく、研究の目的とマーケティング戦略に深く関わる戦略的な決定と言えるでしょう。
ヒト試験の費用相場は?目的別の料金プランを解説
ヒト試験の実施を検討する上で、最も現実的な課題の一つが費用です。試験の費用は、その目的や規模、科学的な厳密性のレベルによって、数十万円から数千万円単位まで大きく変動します 。ここでは、目的別に費用の目安と、価格を左右する要因について具体的に解説します。
目的別に見る費用の目安(エビデンス取得~機能性表示食品届出)
ヒト試験の費用は、求めるエビデンスの「強度」に比例して高くなる傾向があります。目的を明確にすることで、必要な投資レベルを見極めることができます。
- ① 初期探索・社内データ用(費用目安:150万~300万円)
開発の初期段階で、素材の有効性の有無を探索的に確認するための試験です。試験参加者数が少なく(例:10名前後)、プラセボを設けない前後比較試験などが該当します。広報用の参考データや、本格的な試験に進むかどうかの判断材料として活用されます。 - ② 販促・広告の裏付けデータ用(費用目安:200万~500万円)
製品のマーケティング活動や広告表現の科学的根拠として使用するための、より質の高いデータを取得する試験です。プラセボ対照を設ける場合もありますが、機能性表示食品の届出基準を満たすほどの厳密性ではないことが多いです。 - ③ 機能性表示食品 届出用(費用目安:1,000万~5,000万円以上)
消費者庁への届出を目的とした、最も厳格な試験です。費用は高額になりますが、それに見合う科学的根拠の質が求められます。CRO(開発業務受託機関)が提示する料金プランでは、「体脂肪を減らす」という訴求で、試験参加者数60名・12週間の試験で約1,000万円 、別のCROでは機能性表示向けプランが約990万円から といった例が見られます。トクホ(特定保健用食品)申請を目指す場合や、より万全を期した大規模な試験では、5,000万円を超えることもあります 。
この価格差は、単なる規模の違いではありません。価格は、その試験が持つ「エビデンスとしての強度」を反映していると考えるべきです。低価格の試験は、あくまで内部的な示唆を得るためのものです。一方、1,000万円を超えるような高価格の試験には、プラセボ対照、二重盲検法、ランダム化といった科学的信頼性を担保する手法、CTやDXAといった高精度な測定、そのデータを不正なく扱うための措置、そして規制当局の審査に耐えうる厳格な統計解析と報告書の作成といった、数多くの要素が含まれています。したがって、試験費用は単なるコストではなく、規制上のリスクを低減し、製品の信頼性を購入するための戦略的投資と捉えることが重要です。
費用を左右する要因とは?(試験参加者数・期間・測定項目)
ヒト試験の総費用は、主に以下の3つの要因の組み合わせによって決まります。
- 試験参加者数(例数):試験参加者の数が増えれば、募集費用、スクリーニング費用、試験参加者への負担軽減費、そして全ての測定費用が人数分増加するため、コストは直接的に上昇します。
- 試験期間:試験期間が長くなるほど、提供する試験食品のコストが増えるだけでなく、試験参加者の管理やフォローアップの手間も増大します。特に、途中で測定を行う「中間測定」を追加すると、その分の来院・検査費用が上乗せされます 。
- 測定項目:評価する項目が増えれば、その分コストも増加します。特に、CTやDXAのような高価な画像診断や、詳細な血液検査などを追加すると、費用は大幅に上がります。また、プロトコルの作成や統計解析、最終報告書の作成といった専門的な作業にも、それぞれ費用が発生します。
- データの取り扱い:試験を実施運営する機関とデータを取り扱う期間は一般的には資本関係や事務局の運営など介入されていない方がデータの信憑性が高くなります。食品CROはこの辺りを兼務して価格を落としている企業と多少価格は高くなりますが、データの信憑性を高めるために別々の企業で実施している企業もあります。
これらの要因は独立しているわけではなく、互いに影響し合ってコストを増大させます。例えば、試験参加者数を20名から40名に倍増させると、募集費用だけでなく、40名分のCTスキャン費用、40名分の血液検査費用が必要となり、コストは単純に2倍以上に膨れ上がることがあります。また、試験期間を6週間から12週間に延長し、中間測定を1回追加した場合、試験参加者1人あたりの来院回数と検査セット数が倍増し、総費用に大きく影響します。このように、試験計画における一見小さな変更が、最終的な予算に大きなインパクトを与える可能性があることを理解し、計画段階で慎重に検討することが求められます。
20年以上の実績と経験があるアポプラスステーション株式会社
→ヒト試験について無料でお問い合わせする
信頼できるCRO(開発業務受託機関)の選び方
ヒト試験の成功は、信頼できるパートナー、すなわちCRO(Contract Research Organization:開発業務受託機関)の選定にかかっていると言っても過言ではありません。CROは単に試験を代行するだけでなく、計画段階から規制当局への対応までをサポートする戦略的パートナーです。ここでは、最適なCROを選ぶための重要なポイントを解説します。
実績と専門領域の確認ポイント
CROを選定する際、まず確認すべきはその実績と専門性です。市場には多くのCROが存在しますが、それぞれに得意な領域があります。
- 「体脂肪」領域での実績:まず、そのCROが「体脂肪」や「メタボリックシンドローム」関連の試験を豊富に経験しているかを確認します 。ウェブサイトなどで、具体的な試験実績や論文発表のリストが公開されているかは重要な判断材料です。
- 専門性と技術力:自社が求める測定方法に対応可能かどうかも重要です。CTやDXAといった高度な測定機器を用いた試験の実施経験があるかを確認しましょう。
- CROごとの強みの見極め:各CROは独自の強みで差別化を図っています。自社の製品特性や開発フェーズに最も合致した専門性を持つCROを選ぶことが、プロジェクト成功の確率を高めます。
届出サポートから論文作成まで:ワンストップサービスの価値
優れたCROは、試験の実施だけでなく、その前後のプロセスまでを包括的にサポートする「ワンストップサービス」を提供しています。
- 上流から下流までの一貫サポート:理想的なパートナーは、試験計画(プロトコル)の策定、倫理委員会への申請、試験参加者募集、試験実施、データマネジメント、統計解析、そして最終報告書の作成まで、すべてのプロセスを管理してくれます。
- 規制当局への対応力:特に機能性表示食品の届出を目指す場合、届出書類の作成代行や、消費者庁からの問い合わせ(差し戻し)への対応サポートは非常に価値のあるサービスです 。
- 科学的価値の最大化:さらに、試験結果を学術論文として専門誌に投稿したり、学会で発表したりするためのサポートを提供しているCROもあります 。これにより、試験結果は規制対応だけでなく、企業の技術力や製品の科学的価値を広くアピールするための資産となります。
製品開発から市場投入までの道のりは長く、複雑です。研究開発から試験実施、統計解析、規制対応、学術発表といった各段階で担当者や委託先が変わると、情報の断絶や手戻りが発生するリスクが高まります。これら全工程を一つのCROが一貫して管理するワンストップサービスは、単なる利便性の提供に留まりません。それは、計画の初期段階から最終的なゴール(規制当局への届出や特定のヘルスクレーム)を見据えた、無駄のない最適な試験設計を可能にする、プロジェクト全体のリスクを低減するための極めて有効な戦略なのです。CROは単なる業務委託先ではなく、事業目標を共有し、共にリスクを管理する戦略的パートナーとして選ぶべきです。
20年以上の実績と経験があるアポプラスステーション株式会社
→ヒト試験について無料でお問い合わせする